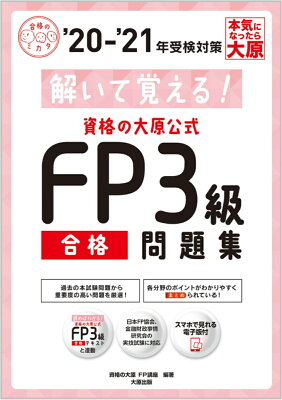FP3級の合格を目指して正しい知識を学びましょう。
今回は2019年1月に行われたFP3級試験の〇×問題の内答えが〇、すなわち記述内容が正しいものを一気に紹介します。
私がよくやる正しい知識を雑多にインプットして知識の下地を作っていく勉強法です。
【問題1】
ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められている。
【問題4】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
【問題5】
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。
【問題6】
国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。
【問題7】
学資(こども)保険には、出生前加入特則を付加することにより、被保険者となる子が出生する前であっても加入することができるものがある。
【問題13】
元金1,000,000円を年利1%の1年複利で2年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、1,020,100円である。
【問題14】
ある債券の信用リスク(デフォルトリスク)が高まった場合、一般に、その債券の価格は下落し、利回りは上昇する。
【問題17】
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
【問題19】
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【問題21】
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。
【問題23】
建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
【問題25】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
【問題28】
遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。
【問題29】
取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができる。
慣れてきたら実際に問題を解いて覚えましょう。
生活を豊かにするため、マネーリテラシーを高めましょう。